俳句では「祭」は夏の季語である。
夏祭りについて、ウィキペッディアは、「日本において夏に行われる祭りの総称である。なかでも7月上旬から8月下旬頃のものを指すことが多い。逆に9月以降の祭りは旧暦7月に行われる場合は夏祭りに準じて扱われることが多い」
と解説。
しかし俳句の季語である祭は、5月開催の葵祭を指す。

フリー画像から↑
新暦5月の葵祭が、祭の代表で、「祭」が夏の季語に指定された。
それ以降数多くの祭が制度化された。
今日夏祭りといえば、近在の神社で行われるものを指すので、
俳句でも「夏祭」という使用を認めるべきであろう。
- 祝辞みな未来のことや植樹祭 田川飛旅子 『植樹祭』
- 祭の村祭支度の村にも鵙 茂里正治
- 立読や神田祭の陰祭 斉藤夏風
- 空馬が走りに走り野馬祭 行方克己 昆虫記
- しやくり上げしやくり上げては祭の子 行方克己 昆虫記
- 妹のそののち知らず獺祭忌 行方克己 知音
- 文庫本竹の里歌獺祭忌 行方克己 知音
- 笛吹いて神を寝かさぬ雪祭 稲垣陶石
- 玉取祭済みし参道ずぶ濡れに 鮫島春潮子
- 荒御魂さながらに走せ繞道祭 佐野美智
- 繞道祭火屑を蹴つて禰宜走る 民井とほる
- 御神火の火屑掃き寄す繞道祭 村上冬燕
- いよ~に左義長祭夜に入りぬ 高田風人子
- 八方の嶺吹雪きをり成人祭 福田甲子雄
- 花舗の燈や聖誕祭の人通る 大野林火
- 年越祭影あつまりて人となる 滝 南窓
- 飾られて脚太き馬おん祭 斉藤敏子
- 救護所の人も裃おん祭 茨木和生
- おん祭馬行列をはみだして 塩川雄三
- 演能にとゞまる渡御やおん祭 大橋敦子
- おん祭春日乙女が神馬曳き 本多炬生
- お出ましもお還りも夜やおん祭 右城暮石
- 藤色を貴び春日おん祭 塚田青女
- 夜祭の桟敷に火桶配らるる 立木塔児
- 桑枯れて秩父夜祭来りけり 岡田水雲
- 秩父夜祭とは聞くだにもあな寒や 富安風生
- 鎌とりて神農祭の巫女の舞 廣瀬ひろし
- 神殿も御簾巻きあげる踏鞴祭 村上冬燕
- するめ焼くにほひも恵比須祭かな 瓜生和子
- 鞴祭鉄の山に塩を撒く 藤井艸眉子
- 一門の鞴祭のあとの酒 三木朱城
- 鞴祭燧石にて火を創り 平野照子
- 朝鵙や神在祭の列につく 角川源義
- 神在祭十九社開かずの扉を開けて 村瀬水螢
- 奉納の繭も慈姑も新嘗祭 三谷いちろ
- 神の田の祭のごとし初霰 永方裕子
- 稲の花こぼれて島の火の祭 本谷久邇彦
- 斑鳩の穂田に雨ふる祭あと 民井とほる
- 鬼灯の熟れて袋のなか祭 檜 紀代
- 椋の実の梢噴きあげて火の祭 三嶋隆英
- 祭くる木曽の晴夜の白芙蓉 福田甲子雄
- 韓神の祭にささぐ青秋刀魚 佐野美智
- 秋鯖をしめて祭の一品に 小泉美保子
- かりがねや湖北は祭多き村 青柳志解樹
- 獺祭忌漁火ひとつ明るくて 千田一路
- 柿二つ一つは渋き獺祭忌 中谷孝雄
- 寺を出て寺に戻れり牛祭 三島晩蝉
- 子供らにねむき呪文や牛祭 岸風三楼
- 牛迎ふ提灯ひとつ牛祭 太田穂酔
- 大牛を恐るゝ児あり牛祭 五十嵐播水
- ねぎらひてぬぐふ涎や牛祭 三嶋隆英
- 時代祭手持無沙汰の龍馬ゆく 中井眸子
- 疲れたる時代祭の禿かな 松村花舟
- 時代祭ほたほたかなし馬の糞 きくちつねこ
- 茶道具の一荷も時代祭かな 岸風三楼
- 惜しみなく地擦る束帯時代祭 西本一都
- 御所の木々粧ひそめし時代祭 畑 紫星
- 時代祭華か毛槍投ぐるとき 高浜年尾
- 白雲に時代祭の毛槍飛ぶ 辻本斐山
- 火伏祭の一の火つきし鳥居前 肥田埜勝美
- 浅間祭天下御免の火を燃やす 阿部朝子
- 火の祭富士の夜空をこがしけり 角川源義
- 中仙道秋の祭の山車一つ 大澤ひろし
- 辻ごとに樽酒そなへ秋祭 野村多賀子
- 島の名を氏とし住めり秋祭 村上杏史
- 外股におかめが舞ふよ在祭 槫沼清子
- 極まりは神主も馳す浦祭 田川飛旅子
- 秋祭すみ麹室開け放つ 佐々木経子
- 提灯を木深くさげぬ秋祭 富田木歩
- 豆腐屋が寄附を集めに秋祭 阿部みどり女
- 希ふこと少なくなれり星祭 品川鈴子
- 峡の温泉はひそやかなれど星祭 加藤楸邨
- 西陣や裂に歌書く星祭 薄木千代子
- 鰯舟祭具浄むる波に着く 米沢吾亦紅
- 廻廊に秋の汐満つ献茶祭 木村里風子
- 秋風や石に香焚く古墳祭 小原啄葉
- 射干の花大阪は祭月 後藤夜半
- 紅花の祭最中の出羽に入る 石川幸子
- 大阪の祭つぎ~鱧の味 青木月斗
- 早鉦の執念き天満祭かな 西村和子
- みちのくは雲湧きやすし野馬祭 古賀まり子
- 気負ふなき百姓馬や野馬祭 篠田悌二郎
- くらやみの船紅や天神祭 金子 晉
- 武者の馬祭酒吹き浄めけり 勝又一透
- 舟べりに酔ひ寝の漁夫や管絃祭 林 徹
- 満潮のここぞと管絃祭さかる きくちつねこ
- 厳島管絃祭に月の波 皆川盤水
- 田草取る仕草も舞ふて田植祭 三井日月夫
- 田祭や草木を渡るあゆの風 前田普羅
- 大団扇三社祭を煽ぎたつ 長谷川かな女
- 神遊ぶ三船祭の水ゆたか 太田由紀
- 葵懸け遊びつつくる祭馬 加藤三七子
- 荷風なし万太郎なし三社祭 宇田零雨
- 地下鉄を出るより三社祭かな 倉田春名
- 御車はうしろさがりや賀茂祭 後藤夜半
- 三社祭露地の稲荷も灯りけり 岩井愁子
- 一と日のびし葵祭や若葉雨 高橋淡路女
- 神輿太鼓雨に跳ね打つ鍋祭 三木蒼生
- 鍋雫雨の筑摩の祭稚児 伊藤柏翠
- 路地に生れ路地に育ちし祭髪 菖蒲あや
祭の例句、俳句検索には1800句以上収録されている。
まさに葵祭を指すもの、むしろ希少である。
有名な祭でない場合は、他の季語と重ね使いしているのが一般的。
「夏祭」の例句もけっこうある。いまさら夏祭という使い方を認めろと叫ぶ必要もないみたい。
- 梢より雲のおりきし夏祭 原裕 『新治』
- 鴨居より木槍をはづす夏祭 長谷川双魚 『ひとつとや』以後
- 夜と昼といづれが故郷夏祭 長谷川双魚 『ひとつとや』
- 読まず書かぬ月日俄に夏祭 野澤節子 『未明音』
- 夏祭戊辰の役の兵揃ふ 荒井英子
- 読まず書かぬ月日俄に夏祭 野沢節子
- 雨をよぶ山車を出しけり夏祭 長谷川かな女
- 好きな子のそばには行けず夏祭 村松壽幸
- 川あれば町ありて夏祭あり 佐土原岳陽
- すぐ途切れ山国に会ふ夏祭 加藤瑠璃子
- 刺青の牡丹のさわぐ夏祭 水原春郎
- 繭買のはりこむ寄附や夏祭 藤原如水
- 夏祭水田水田を笛ころび 石川桂郎
- 夏祭まへや大工ののみ光り 百合山羽公
- 真円き月と思へば夏祭 中村汀女
- 山麓の遠ちの一村夏祭 欣一
- 浦の子のこんなにゐしや夏祭 上崎暮潮
- 叱られし子の眼に紅き夏祭 齋藤愼爾
- まはだかの男がよけれ夏祭 筑紫磐井 婆伽梵
- 夏祭噴煙街に倒れくる 米谷静二
- 花だしに跨る人や夏祭 芦田秋窓
- いもうとの魚締めにくる夏祭 下田稔
- 赤きものまた一つ減る夏祭 宇多喜代子 象
- 万太郎あらず浅草夏祭 吉屋信子
- 開けはなつ閾の艶の夏祭 鷲谷七菜子
- わが部屋は四階地には夏祭 斉藤夏風
- 茶問屋に茶壷茶唐櫃夏祭 辻田克巳
- 眼帯の方の目でみる夏祭 宇多喜代子
- いくさなき人生が来て夏祭 橋本夢道 無礼なる妻
- 町の上に残間が青し夏祭 相馬遷子 山國
- どぜうやの大きな猪口や夏祭 久保田万太郎 流寓抄以後
- 梢より雲のおりきし夏祭 原裕 新治
神津神社の夏祭りは、22日、23日
ここも布団太鼓が主役のよう
予定表では運び込まれたところだが、辺りには人影なし
宵宮のために屋台が数軒準備中。昨日の午後。

























































































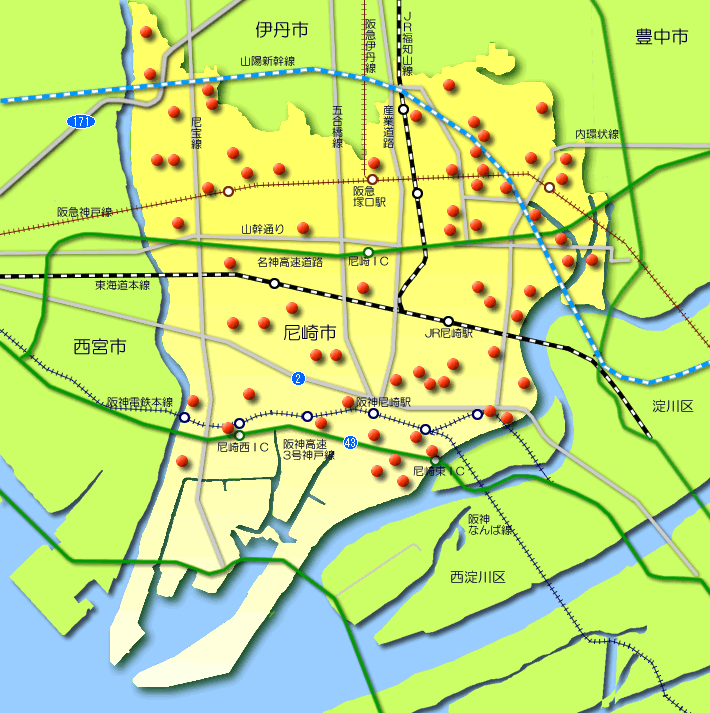
































 向き合った2基のだんじりが、ウイリーのように後ろのコマだけで立ち上がり、そのまま正面からぶつかり合う。前方にツノのように突き出した肩背(かたせ)と呼ばれる棒を上に載せた方が勝ちというルールは「指相撲みたいなもの」と言うのが分かりやすい。各対戦は15分の制限時間があり、だいたい3~4回ぶつけ合って上を取った回数が多い方が勝ち、となる。勝敗の行方は傍目には分かりにくく、「えらいやっちゃ」と喜んでいる方が勝ち、と覚えておくとよい。
向き合った2基のだんじりが、ウイリーのように後ろのコマだけで立ち上がり、そのまま正面からぶつかり合う。前方にツノのように突き出した肩背(かたせ)と呼ばれる棒を上に載せた方が勝ちというルールは「指相撲みたいなもの」と言うのが分かりやすい。各対戦は15分の制限時間があり、だいたい3~4回ぶつけ合って上を取った回数が多い方が勝ち、となる。勝敗の行方は傍目には分かりにくく、「えらいやっちゃ」と喜んでいる方が勝ち、と覚えておくとよい。 事前にくじで選んだ対戦表に沿って、各町4回ずつ山合わせをおこなう。昨年の雪辱に燃える町や、宿命のライバル対決に盛り上がる町などその心中は様々。しかし、この勝負に審判はおらず、「○○町の勝ち」というようなジャッジを下すことはない。多くの観客が見守る中、勝敗を決するのは、その場が持つ独特の空気。対戦結果を誰かが記録するわけでもないが、街の記憶が山合わせの大一番を語り継いでいるのだ。
事前にくじで選んだ対戦表に沿って、各町4回ずつ山合わせをおこなう。昨年の雪辱に燃える町や、宿命のライバル対決に盛り上がる町などその心中は様々。しかし、この勝負に審判はおらず、「○○町の勝ち」というようなジャッジを下すことはない。多くの観客が見守る中、勝敗を決するのは、その場が持つ独特の空気。対戦結果を誰かが記録するわけでもないが、街の記憶が山合わせの大一番を語り継いでいるのだ。











































































































