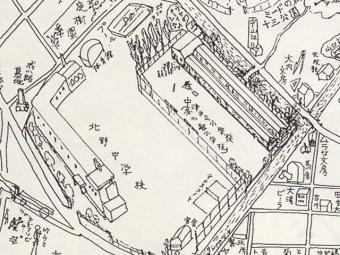暮らし~の のHPより
暮らし~の のHPより
レットロビンとは、カナメモチ属に分類されている常緑性の高木です。レットロビンは、日本産のカナメモチとオオカナメモチがアメリカで掛け合わされてできた植物です。樹高10mにまで成長し、春になると白くてとてもかわいい花を咲かせてくれます。新芽は赤色をしていてとても美しく、花も新芽も楽しむことができます。
私はカナメモチないしレッドロビンを「アカメカシワ」と呼んでいたことがある。
ウィキペディア:
アカメガシワ(赤芽槲、赤芽柏、Mallotus japonicus)は、トウダイグサ科アカメガシワ属の落葉高木。新芽が鮮紅色であること、そして葉が柏のように大きくなることから命名された説もあるが、柏が生息していない地域では、この木の葉を柏の葉の代用として柏餅を作ったことからアカメガシワと呼ぶようになったとの説もある。古来は熱帯性植物であり、落葉性を身につけることで温帯への進出を果たしたものと見られる。古名は楸(ひさぎ)。
この解説よりもそれ以下の文で思い当たることがある。あちらこちらで芽吹く赤芽の
幼木。
日本の本州の岩手・秋田県以南、四国、九州のほか、アジアでは台湾、中国の南部の山野に自生する。日本では二次林に多く、山野、平地、川の土手のほか、空き地などによく生えてくる、典型的なパイオニア植物である。雌雄異株の落葉高木で、樹高は5〜10mに達する。春に出る若葉は、鮮やかな紅色をしており美しく[1]、星状毛が密生する[2]。
パイオニア植物であるという記述。他の家の庭を整備している庭師に聞いたことある。
アオキという回答だったが、違うと思った。
- 碑の陰の碑に黐の花雪白に 加藤知世子
- 黐の花ここだく散りて侍町 松崎鉄之介
- 想ひ出の石窪に鳥黐を搗く 中溝 八重子
- 渡り来し小雀は黐につき易き 太田鴻村
- 夕月は水色なせり黐の花 草間時彦
- 掌をあてて散る枝散らぬ枝黐の花 加倉井秋を
- 黐ちるや蟇こもりゐる垣の下 村上鬼城
- 七ツ星光る山家や黐匂ふ 岡田日郎
- 虚空には日の流れをり黐の花 水野爽径
- 仏陀笑むおぼろに黐の花振りて 内田秀子
- 黐の花神秘は人の眼に見えず 三橋鷹女
- 夕凪の黐木斛にきはまりぬ 渡邊千枝子
- 懸命に装ふがよし黐の花 本田秋風嶺
- 同じ道とりてもどらぬ黐の花 畑井政蔵
- 夕べまでいつもひとりや黐の花 星野すま子
- 夕月は水色なせり黐の花 草間時彦
- 黐の花こぼるる風の重さだけ 能村登四郎
- とり出でて花散る黐に蚊帳を干す 西島麦南
- 医師の来て垣覗く子や黐の花 富田木歩
- 禽むるる大椿樹下に黐搗けり 飯田蛇笏
- 黐つくや蒼蝿の賦に書き漏らし 青木鷺水
- 黐の花人集まつてゐる暗さ 和田耕三郎
- 夕月は水色なせる黐の花 草間時彦
- 黐の木の余技こまごまと花降らす 中尾壽美子
- 黐の花こぼるる花の重さだけ 能村登四郎
- 暗がりに黐の木のある夏休み 藤田あけ烏 赤松
- 黐散りぬ見得の写楽の終焉地 山内遊糸
- 機嫌悪き日や八方に黐の花 草間時彦
- 躁の雨を手で拭く黐の花 松岡隆子
- 黐ちるや蟇こもりゐる垣の下 村上鬼城
- 額咲いて黐さいて梅雨古きかな 市川東子房
- 暗くなる黐の木を見つ木歩の忌 下田稔
- 黐咲くや降るともなしに道濡れて 荒井正隆
- 黐棒の蠅のうなりや駄菓子店 会津八一
- 黐咲いて照り放題の川の面 岡本眸
- 着ゆるめて黐の花降る薄日かな 渋谷道
- マタニティ妹に譲る黐咲くころ 田川飛旅子
- 眠る山黐埋め穴に埋め終へし 内田百間
- 木斛か黐か知らねど朝曇 久保田万太郎 草の丈
- 黐の花こぼれたければ匂ふなり 後藤比奈夫 花匂ひ
- 水とりや心の闇の流し黐(もち) 黒柳召波 春泥句集
- 鳥黐の香やこどもらとすれちがふ 赤城さかえ
- 桐もやゝ黐皀角も芽をぞふく 加舎白雄
- 目白捕る黐をコツコツ叩きをり さざなみやつこ
俳句で黐といえば、クロガネモチやネズミモチではなく、トリモチを作るホンモチを指す。
それを知らずに、私はもっぱらクロガネモチを黐として詠っていた。
今朝の家の近くの桜
今朝の近隣公園の桜
夜桜
一組1家族3人が寂しくい宴
相変わらず寒い。開花時の予報では、神戸(王子動物園)の満開は4月3日、
大阪(大阪城公園)の満開は4月5日であったが、1日2日ずれるかも。
今日の段階で近隣公園ではよく咲いている木で8分他は5分程度。